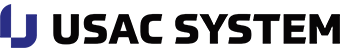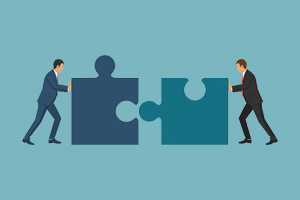お客様サポート
製品をご利用中の方へ

ライセンス管理システム(UIS)
UIS(ユーイス)[USAC information share] はお客様と情報を共有するためのシステムです。
製品や証書のダウンロード、パスワード再発行依頼、バージョンアップ依頼などが行えます。
※製品納品時にご案内した情報でのログインが必要です。

ライセンス交付申請
“名人シリーズ”をインストールした企業様は、こちらの窓⼝からパスワードの発⾏をご申請願います。
※ハードウェアプロテクト(USBタイプ)をご利用の場合、申請は不要です。
※申請には、ログインIDとシリアルNo.が必要です。

WebFAQ
お客様からよくいただくお問合せとその回答をQ&A形式でまとめました。

バージョン履歴情報
「名人シリーズ」のバージョン履歴情報です。各バージョンのリリース⽇や主な改良点を記述しています。