
堺ヤクルト販売株式会社 様
堺ヤクルト販売におけるDX推進:RPA導入から全社的な生産性向上への挑戦
社内SEとしてグループ全体で導入している基幹システムのメンテナンスを担当しながら、現場が抱えている課題と解決策を洗い出し。RPA活用と従業員の情報リテラシー向上から始めたDX推進。
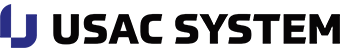

生産性と作業品質の向上を実現する業務自動化ソリューション。
Windowsアプリの操作からブラウザ操作、メールを伴う業務の自動化まで、
稼働安定性を重視したRPAソリューションをご提案します。

個別の業務・製造プロセスをデジタル化することで業務を効率化
生産性向上や付加価値をつけることにより、より顧客満足度を高める
ご提案をいたします。
取引先ごとの対応が必要な業務のシステム化が迅速行え、基幹システムとも柔軟に連携いたします。
指定伝票や送り状、荷札ラベル、指定請求書、値札など、企業内で発生するあらゆる帳票の発行や、倉庫内検品システムのご提案なら「名人シリーズ」にお任せください。

堺ヤクルト販売株式会社 様
社内SEとしてグループ全体で導入している基幹システムのメンテナンスを担当しながら、現場が抱えている課題と解決策を洗い出し。RPA活用と従業員の情報リテラシー向上から始めたDX推進。

花王グループカスタマーマーケティング 様
受発注業務をミスなく、迅速に処理をしたい。DXのボトルネックであったファクスからの脱却をスマホアプリ「Pittaly Order」で実現

自社事例<電子帳簿保存法業務の自動化>
RPAとClimberCloudの連携で電子取引のデータ保存を自動化。
新たな業務負荷ゼロで電帳法対応を実現。
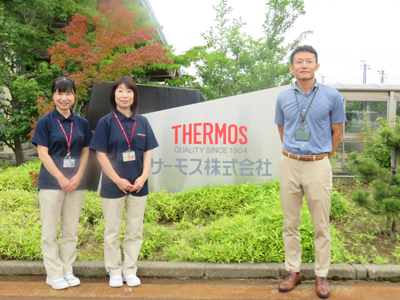
サーモス株式会社 様
中期計画で全社的業務効率化の号令
長年の課題だった出荷業務改善を送り状名人で実現

物流
物流センターにおける主要な課題の一つに、出荷の最適化と帳票処理の効率化があげられます。出荷プロセスの合理化や送り状のデジタル化を進めることで、オペレーションの正確性と迅速性が向上し、競争力のある物流センターの運営を実現することが可能です。

業務改善
業務のデジタル化推進は、伝票発行・処理などの事務業務でも例外ではありません。DXやペーパーレスの文脈で、紙やアナログな作業は効率化に向かっており、弊社の指定伝票発行システム「伝発名人」も、ペーパーレス対応や業務効率化をさらに支援します。

コスト削減
IT導入補助金がさらに利用しやすくなりました。2023年は「通常枠」で補助下限額が引き下げられたほか、クラウドサービス利用料の対象期間が1年から2年に拡充されるなど、さらに充実しています!ぜひ、IT導入補助金の利用をご検討ください。

物流